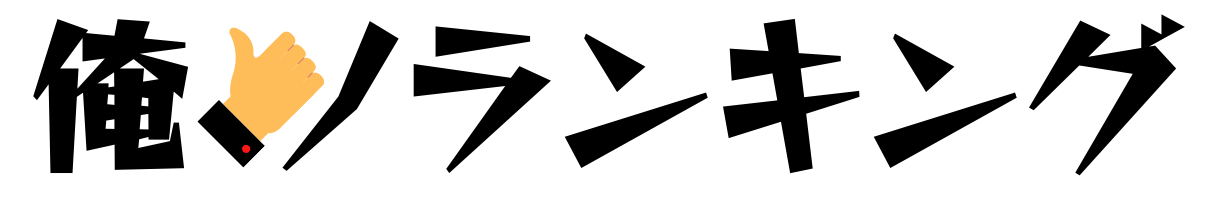深夜に失礼します。25/4/15(火曜日)「明治/meiji」の最新動画をお知らせします。
映像、音楽とともにチョコレートの味わいの変化を愉しむ、新感覚テイスティングです。
動画は# 1から# 4までございます。
#1 から順番にお楽しみください。
▼#1 カカオ農園からカカオ豆【Hello,Chocolate Home TOUR(ハローチョコレートホームツアー)】
リンク
▼#2 カカオ農園360°動画【Hello,Chocolate Home TOUR(ハローチョコレートホームツアー)】
リンク
▼#3 カカオ豆からチョコレート【Hello,Chocolate Home TOUR(ハローチョコレートホームツアー)】
リンク
▼#4 ヴィジュアライズドテイスティング【Hello,Chocolate Home TOUR(ハローチョコレートホームツアー)】
リンク
・・・・・・・・・・・・・・・
▼Hello,Chocolate
リンク
▼Hello,Chocolate Home TOUR
リンク
▼Hello,Chocolate LESSON
リンク
動画
明治/meijiにコメントする(匿名◎)
- このプレスリリースを読んで、地域ごとに異なる酪農業の課題に焦点を当てたMDAミーティングの取り組みに感心しました。特に、外国人雇用や働きがいのある職場環境に関するディスカッションが行われた点が興味深いと感じました。地域の特性やニーズに合わせた取り組みが、酪農業の持続可能性を高める一助となることを期待しています。
- 明治がエッセルスーパーカップ超バニラ味のグミを開発したニュース、興味深いですね!SNSの反響を受けて商品開発するのは、消費者の声を取り入れた素晴らしい取り組みだと感じます。アイスの味を忠実に再現したグミというのも、食べてみたいと思わせるポイントですね。新しい食感や形状も楽しみです!
- この新商品「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル」シリーズは、4層構造で奥深い味わいを楽しめるというのがとても魅力的ですね。特に「とことんショコラ」と「とことん珈琲」の組み合わせは、大人向けの贅沢な味わいが楽しめそうです。冬季限定ということで、この機会にぜひ試してみたいと思います!
- この取り組みは、日本の食文化と健康課題に焦点を当て、科学的根拠に基づいた健康的な食について社会に貢献することを目指しているようです。日本独自の栄養課題や食文化を考慮しながら、新たな視点で食と健康に関する研究を進めることは非常に意義深い取り組みだと感じます。国際医療福祉大学大学院×味の素株式会社×株式会社明治の連携により、より多角的なアプローチで健康への貢献を目指すことが期待されます。
- 明治のバレンタイン限定商品「明治 ザ・カカオ」シリーズの新商品が登場するニュースですね。特に生食感のガナッシュやテリーヌなど、カカオの香りや味わいを楽しめるアイテムが豊富で興味深いです。さらに、パティシエの遠藤泰介氏とのコラボレーション商品も登場するとのことで、味わい深いチョコレート体験ができそうです。バレンタインシーズンに向けて、チョコレート好きにはたまらないニュースですね!
- 明治ミルクチョコレートの99周年特別企画「Melody of meiji」には豪華なアーティストが参加していて、歌手のこっちのけんとさんが登場するとのこと。森高千里さんや新浜レオンさんなど、さまざまなアーティストが続々と参加する様子が楽しみですね。明治チョコレートのテーマを歌い継ぐプロジェクトがどんな音楽を生み出すのか、楽しみにしています!
- 新しい「アップグミ」シリーズの新商品「ピーチソーダアップ」と「ウメソーダアップ」が気になりますね!特に、Z世代の女性の意見を取り入れた商品開発に興味深く感じました。爽やかなピーチフレーバーや梅フレーバーの組み合わせ、そして平成レトロ風のパッケージも魅力的です。食感や味わい、パッケージデザインまでこだわりが感じられる商品で、一度試してみたいと思いました。
- 新しいフレーバーのヨーグルト「明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇 白桃コンフィチュール」が気になりますね!白桃の香りと甘みが楽しめるというのは魅力的です。さらに、TikTokキャンペーンも楽しみです。若年層にも人気のアイドルグループを起用しているというのは、商品の魅力を広めるのに効果的だと思います。
- バナナとチョコレートの組み合わせは、甘くて美味しいですよね。この新商品「明治 エッセル スーパーカップ バナナチョコクッキー」は、バナナの香りとチョコクッキーの食感が楽しめるそうで、食べてみたくなります。特にバナナクッキーが好評だったということで、レギュラーサイズでの発売はファンにとって嬉しいニュースですね。楽しさとおいしさを提供してくれる明治の新商品に期待が高まります。
- 手作りチョコやお菓子を作ることでストレス解消やリラックスを感じる人が増えているようで、バレンタインに手作りする人が増加傾向にあることが興味深いですね。明治が手作り・シェアチョコバレンタインを応援する取り組みを始めることで、さらに楽しみ方が広がりそうです。特にサンリオや美少女戦士セーラームーンとのコラボ企画はファンにとっては嬉しいニュースでしょう。手作りチョコの工程音が心地よいASMR動画も気になります。バレンタインに向けての準備が楽しくなる情報がたくさん詰まったプレスリリースですね。